2025年1月22日
2024年度TFC×TEL協働プログラム公開シンポジウム「デジタル×サステナブル社会のデザイン」を開催しました
2025年1月22日(水)10:00–17:45、2024年度TFC×TEL協働プログラム公開シンポジウム「デジタル×サステナブル社会のデザイン」が、 東北大学 片平キャンパス 知の館 (TOKYO ELECTRON House of Creativity) および オンライン (ZOOM Webinar) にて開催されました。 本シンポジウムは、東京エレクトロン株式会社と、東北大学 研究推進・支援機構 知の創出センターの共同主催で開催されたものです。
知の創出センターでは、急速に進化するデジタル技術が持続可能な未来社会のデザインにどのように寄与しうるかを模索するべく、 東京エレクトロン株式会社との協働プログラム「デジタル×サステナブル社会のデザイン」を2022年度より実施してまいりました。 本協働プログラムは、「産学連携技術探索プロジェクト」「未来社会デザイン塾」「社会実装プロジェクト」という三本柱から成るプログラムです。 本シンポジウムでは、各プロジェクトの活動報告を行うとともに、デジタル技術と持続可能な社会にまつわる諸問題について考えるヒントを提供するべく、 専門家の先生方にもご講演いただきました。皆様が、新たな社会デザインを考えるための一助となれば幸いです。
※ 東京エレクトロン株式会社との協働プログラム「デジタル×サステナブル社会のデザイン」の詳細については、 こちらをご覧ください。
最初に、杉本 亜砂子 東北大学理事・副学長 (研究担当) / 東北大学 研究推進・支援機構 知の創出センター長 と、 長久保 達也 東京エレクトロン株式会社 専務執行役員より、開会挨拶を頂きました。

杉本 亜砂子 氏
(東北大学理事・副学長 (研究担当) / 東北大学 研究推進・支援機構 知の創出センター長)
長久保 達也 氏
(東京エレクトロン株式会社 専務執行役員)
午前中に開催されたセッション1「持続可能社会に向けた新しい価値創造」では、3件の大変興味深い講演が行われました。
基調講演1では、神里 達博 先生 (千葉大学大学院 国際学術研究院 教授) より、「テクノロジーと社会 – ELSI/RRIの観点から」 という題で、オンラインでご講演頂きました。神里先生は、ご専門である科学技術社会論 (STS) の観点から、 戦後の流れを振り返り、科学技術万能時代から科学技術への懐疑の時代を経て、 研究開発の初期段階から倫理的・社会的考慮を組み込むことの重要性を主張する 最近のELSIやRRI (Responsible Research and Innovation: 責任ある/応答的な研究・イノベーション) へ至る流れについて非常に分かりやすくお話し下さいました。
続いて、TFC×TEL協働プログラムで「産学連携技術探索プロジェクト」に携わっていただいている 福島 康裕 先生 (東北大学大学院 環境科学研究科 教授) より、「企業が創造する価値の表現方法」という題でお話しいただきました。 福島先生は、企業活動におけるフットプリント (直接間接に環境や社会に与える悪影響) とハンドプリント (直接間接な環境や社会への貢献) をいかに数量化して、 Net Positiveを達成するか という課題に取り組んでおり、その取組みについてお話し頂きました。

神里 達博 氏
(千葉大学大学院 国際学術研究院 教授)
福島 康裕 氏
(東北大学大学院 環境科学研究科 教授)
三つ目の講演では、荻野 裕史 氏 (東京エレクトロン株式会社 サステナビリティ統括部 部長) より、 「サステナビリティの展開について」という題でご講演頂きました。荻野氏は、 東京エレクトロン株式会社がどのようにサステナビリティをめぐる諸課題に取り組んでいるかについてお話しくださいました。 地球温暖化による気候危機やSDGsへの取組み、さらには、人権問題にも高い意識をもちながら、 経済的価値と社会的価値の調和・融合による企業価値の向上を目指していこうとする東京エレクトロン社の真摯な姿勢が分かる貴重なご講演であったと思います。
その後、12:30 – 14:00 には、会場である東北大学 知の館 1Fラウンジにて、 ポスターセッションが行われ、東京エレクトロンの皆様や学内外の先生方との間できわめて活発な質疑応答が行われました。 学生による7件のポスター発表があり、非常に盛況でありました。

荻野 裕史 氏
(東京エレクトロン株式会社 サステナビリティ統括部 部長)
ポスターセッションの様子
ポスターセッションを挟んで午後に開催されたセッション2「AIと未来社会」では、2件のご講演をいただきました。
午後最初の講演では、竹内 孝 先生 (京都大学大学院 情報学研究科 講師) より、 「データ駆動社会におけるAIの信頼性と意思決定の未来」という題でご講演頂きました。 竹内先生は、現在のAIには予測精度の限界から来る信頼相当性 (Trustworthiness) の問題があることに触れられたうえで、 AIの信頼相当性を向上させて人間の意思決定を支援する未来社会の展望について、さまざまな具体例を交えてお話しくださいました。
続いて、TFC×TEL協働プログラムのメイン・オーガナイザーである 直江 清隆 先生 (東北大学大学院 文学研究科 教授) より、 「人間中心のAI社会とは:未来への責任を考える」という題でお話しいただきました。直江先生は、ご専門である科学哲学・技術哲学の観点から、 人間中心のAI社会の展望についてお話しくださり、 社会的意思決定においてAIが重要な役割を負うようになったときいったいどのような責任の概念が必要になるのかという問題提起がなされました。

竹内 孝 氏
(京都大学大学院 情報学研究科 講師)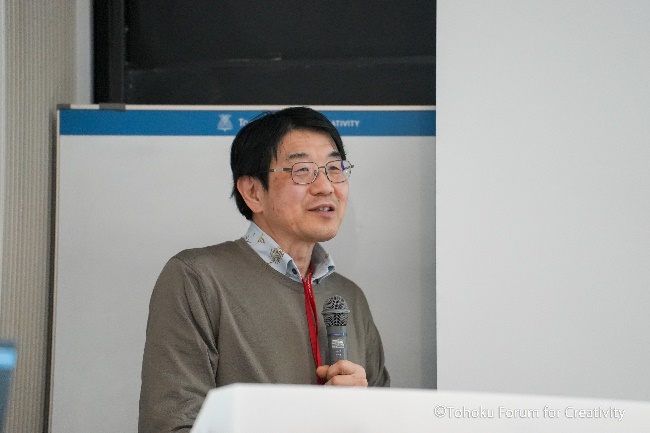
直江 清隆 氏
(東北大学大学院 文学研究科 教授)
セッション3 「TEL協働プログラムの活動から」では、「未来社会デザイン塾」および 「社会実装プロジェクト」の活動紹介および報告も兼ねて、 山内 保典 先生(東北大学 高度教養教育・学生支援機構 准教授) 、 高浦 康有 先生 (東北大学大学院 経済学研究科 准教授) より、お話しいただきました。
山内先生からは、「未来社会デザイン塾の試み:生成AIを活用した未来の寓話づくりプロジェクト」という題で、 未来社会デザイン塾が現在進めている「未来の寓話づくりプロジェクト」についてご紹介いただきました。 これは、生成AIの助けも借りながら未来の寓話を作ることによって、未来社会のあり方を具体的に展望する試みです。 山内先生は、実践例の紹介も交えながら、未来社会デザイン塾のこれまでの取組についてお話しくださいました。
高浦先生からは、「地方創生・ノーマライゼーションとデジタル技術の調和:経済学部生によるフィールド調査報告」という題で、 「社会実装プロジェクト」の取り組みについてご報告いただきました。高浦先生は、学生とともに、 地域企業や地方自治体の関係者の方々との対話しながら地方創生のアイデア提案を行うという取組をされてきております。 経済学部の石田安奈さん、茂木響介さん、佐藤史宗さんが実際に登壇され、 『NFTを通じた地方創生の可能性』という題で、その取組についてご報告いただきました。

山内 保典 氏
(東北大学 高度教養教育・学生支援機構 准教授)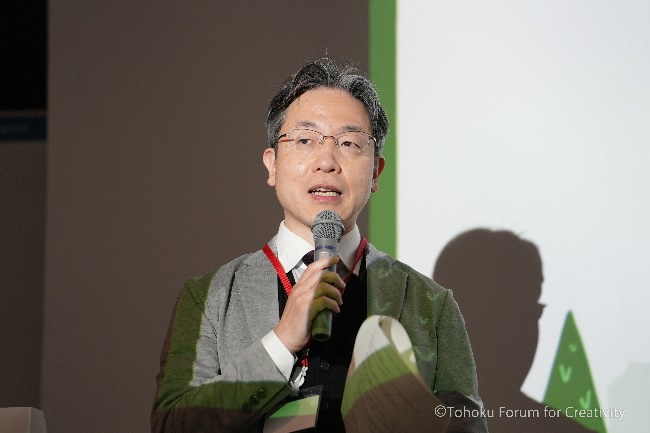
高浦 康有 氏
(東北大学大学院 経済学研究科 准教授)

経済学部生講演の様子

経済学部生講演の様子
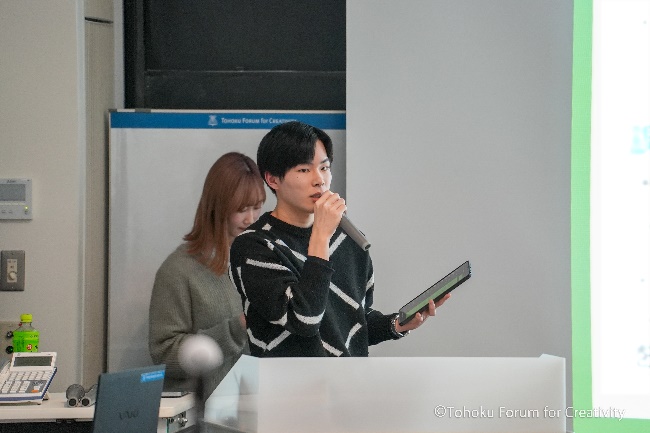
経済学部生講演の様子

会場の様子
指定討論では、直江 清隆 先生をモデレーターとして、荻野 裕史 氏、 神里 達博 先生 (オンライン)、 高浦 康有 先生、 竹内 孝 先生にご登壇いただき、ご議論いただきました。 大変闊達な議論と意見交換が行われ、見ごたえのある討論となったのではないかと思います。

指定討論の様子

指定討論の様子
続いて、東京エレクトロン株式会社 桝永 慎一郎 氏より、ポスター賞の発表が行われました。 ポスター賞は、以下のポスター発表に贈られました。この場を借りて、改めてお祝い申し上げます。
「シリコンウェハに着目した水消費と水資源枯渇リスクの解析」
田中 幸希(東北大学大学院 環境科学研究科 M2)
張 政陽 (東北大学大学院 環境科学研究科 助教)
松八重 一代 (東北大学大学院 環境科学研究科 教授)
最後に、これまでTFC×TEL 協働プログラムの活動にご尽力いただいてきた 山口 光行 先生 (東北大学 研究推進・支援機構 知の創出センター 特任教授) より、 閉会のご挨拶を頂き、無事にシンポジウムを終えることができました。

桝永 慎一郎 氏
(東京エレクトロン株式会社)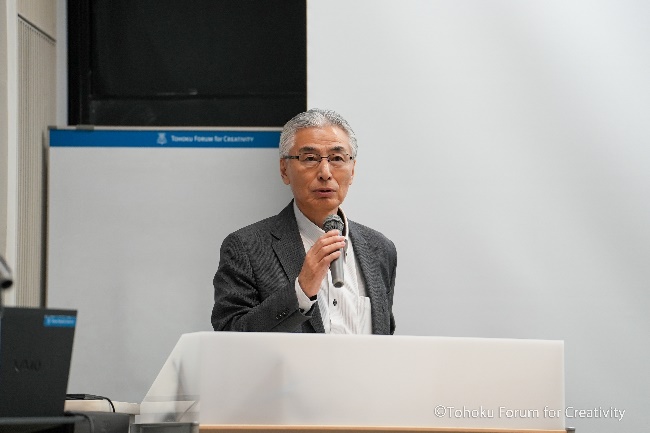
山口 光行 氏
(東北大学 研究推進・支援機構 知の創出センター 特任教授)
今回は、対面とオンラインでの開催でした。大学人、企業の方、また一般の方など多くの方々にご参加いただき、 盛況に開催ができました。たくさんのご参加ありがとうございました。