2025年4月26日
東北大学知のフォーラム2024年度テーマプログラム「未来の食のデザイン」フォローアップイベント 公開講演会「食でつなぐ未来–アフリカと東北大学の協創」を開催しました。
2025年4月26日(土)14:00–16:45、東北大学知のフォーラム2024年度テーマプログラム「未来の食のデザイン」フォローアップイベント公開講演会「食でつなぐ未来—アフリカと東北大学の協創」を開催しました。本講演会は、東北大学知の創出センターと東北大学農学研究科による共同主催、東北大学食科学国際共同大学院プログラムの共催で開催されたものです。
世界が直面する食糧問題の中で、アフリカの食糧問題と持続可能な発展は重要なテーマです。本講演会では、東北大学や海外の研究者、NGO関係者が集い、アフリカの食や農業が抱える問題を取り上げ、未来に向けた解決策を考えることを目的に開催されました。NGOによる現地での取り組みや最新の科学技術の活用など、多角的な視点から議論を深め、持続可能な食の未来に向けた新たな協創の可能性を探りました。アフリカの食や農業、そして未来の食について東北大学との共創を目指した討議がなされました。
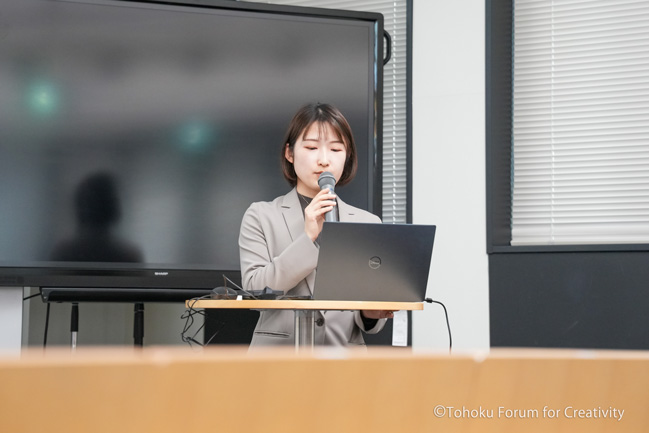
小山 紗江佳 氏
(東北大学大学院 農学研究科)
Afifah Zahra Agista 氏
(東北大学大学院農学研究科)
講演会は東北大学食科学国際共同大学院プログラムの小山 紗江佳 (東北大学大学院 農学研究科 助教)先生とAfifah Zahra Agista(東北大学大学院農学研究科 助教)先生の司会により進められました。
開会にあたり、東北大学理事・副学長(研究担当)・東北大学知の創出センター長である杉本亜砂子先生よりご挨拶をいただきました。2024年度テーマプログラム「Designing food for the future」について、食の未来に関わる課題が重要ということで、当方大学では2024年より、地球規模の食に関わる課題解決を担う博士人材の育成を目指して、「食科学」国際共同大学院プログラム(GP–Food)が開設され、学際的・国際的視点から教育と研究を進めていること、これからアフリカ諸国との連携や若手研究者の育成も積極的に進め、アフリカと東北大学の協働の可能性について、研究者や関係機関の皆さまとの議論を通じて、新たな視点が得られることを期待しているとのお話しをいただきましした。
引き続き講演にはいり、最初に東北大学大学院農学研究科の野地智法先生から2024年度TFCテーマプログラムについてのご紹介をいただきました。2024年度テーマプログラム「Designing food for the future」では、食の未来に関わる課題――人口増加、地球環境の変動、感染症の拡大、食料不均衡といった複合的課題――を見据え、農学、医学、工学、さらには文学などの分野を横断した研究者とともに国際的かつ学際的に議論を重ねてきたこと、このなかで、台湾やインドネシアを含むアジア各国、またアルゼンチンとの研究連携も確立されたことなどをお話しいただきました。

杉本 亜砂子 氏
(東北大学理事・副学長 (研究担当) / 東北大学知の創出センター長)
野地 智法 氏
(東北大学大学院 農学研究科)
続いて、東北大学農学研究科のEustadius Francis Magezi先生による「アフリカにおけるコメの生産性向上:現状と課題」と題する講演がおこなわれました。アフリカでは人口増加や経済成長に伴いコメの需要が急増しており、食料安全保障や貧困削減の観点からもコメの生産性向上が重要とされています。講演では、近代品種や肥料、灌漑、農業機械の活用、技術研修の効果など、現在の取り組みが紹介されました。一方で、灌漑設備や機械化、持続可能な技術の普及など今後の課題についても指摘され、科学的根拠に基づく持続可能な稲作技術の確立の必要性が強調されました。
第3の講演は、一般財団法人ササカワ・アフリカ財団事業課長の菊池翔太朗様から、「環境再生型農業の普及に関する取り組み」についてご講演をいただきました。環境再生型農業とは、土壌劣化や気候変動による生産性低下の問題に対して、単なる生産性の向上にとどまらず、土壌や生態系の回復にも貢献する農業技術です。具体例として、被覆作物の活用による効果について説明された後、技術普及活動による成果の調査研究についてご紹介いただきました。最後、NGOは現場での実践に強みを持つ一方で、科学的根拠に基づいたアプローチを進めるためにはアカデミアとの協力が極めて重要であるとまとめられました。

Eustadius Francis Magezi 氏
(東北大学大学院 農学研究科)
菊池 翔太朗 氏
(一般財団法人ササカワ・アフリカ財団)
菊池先生のご講演のあと10分間の休憩をとり、そのあとは英語で2件の講演をいただきました。
第4の講演者は、Covenant University, NigeriaのYemisi Dorcas Obafemi先生による「Innovative Approaches to Food Security: Lessons from the Covenant–Tohoku University Future Food Project」 というご講演でした。Obafemi先生は、乳幼児の健康に深刻な影響を及ぼすETEC(腸管毒素原性大腸菌)感染症を予防するための研究に取り組まれています。具体的には、免疫機能を有する乳酸菌のスクリーニングおよびその作用メカニズムの解明に取り組まれており、現在は東北大学と共同で腸管上皮細胞株を用いた免疫機能解析を進めておられます。将来的には、乳酸菌を利用した乳幼児向け発酵型補完食の開発を目指しており、講演の中では実際に開発中の補完食を観客に披露しながら、世界中の子どもたちの健康向上に貢献する可能性を秘めていることを強調されました。
最後のご講演は、Egerton University, Kenya のGideon Aiko Obare先生による「Enhancing Global Food Security: Strengthening Japan–Africa Partnerships for Transforming Agriculture Value Chains」のご講演です。Obare先生からは、アフリカの食料安全保障に関する構造的課題と、日本・アフリカ間の協働の可能性についてご講演いただきました。講演では、気候変動による収量減少や経済的損失、ジェンダー格差といった課題が取り上げられ、特に女性の農業資源へのアクセス改善が生産性や経済発展に貢献し得ることが強調されました。また、日本の支援事例としてCARDやSHEPの取り組みが紹介されました。今後の展望として、気候変動に対応した技術導入やジェンダー配慮型技術の開発、地域主導の長期的なパートナーシップ構築の重要性が示されました。

Yemisi Dorcas Obafemi 氏
(Covenant University, Nigeria)
Gideon Aiko Obare氏
(Egerton University, Kenya)
最後に、東北大学大学院農学研究科長・農学部部長の北澤春樹先生から閉会のご挨拶をいただきました。 2024年度のテーマプログラムが成功裡に終了したこと、これを踏まえて農学部や農学研究科では、食の問題解決のための研究を推進しながら、食糧問題のホットスポットであるアフリカ地域の大学との協創を進め、研究成果の実装により社会への貢献を目指していくことをお話しされました。

北澤 春樹 氏
(東北大学大学院 農学研究科長 / 東北大学農学部長)
会場の様子
参加者の方々からは、沢山の質問がよせられ、中にはかなり専門的な質問もありましたが、時間の制約上、すべての質問をとりあげることができませんでした。しかし、事後のアンケートの結果では平均して満足度が高く、参加者の皆様にとっても未来の食について考えるよい機会となったようで、大変うれしく思っております。
今回は、オンラインでの開催であり、仙台市内だけでなく、関東を含めて約70名の方々の参加申し込みがあり、盛況に開催ができました。たくさんのご参加ありがとうございました。